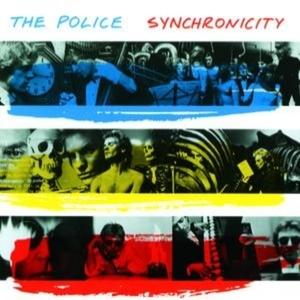 不定期連載企画、懐かしの名盤ジャンジャカジャーンのシリーズ第8弾は、ポリスでお送りしている。ただのロック好きの僕が恐縮だが、これまで真剣に聴いてきたアルバムやライブ音源、インタビューなどを組み合わせ、スーパートリオについて推測たっぷりの私見をぶちかませていただく。
不定期連載企画、懐かしの名盤ジャンジャカジャーンのシリーズ第8弾は、ポリスでお送りしている。ただのロック好きの僕が恐縮だが、これまで真剣に聴いてきたアルバムやライブ音源、インタビューなどを組み合わせ、スーパートリオについて推測たっぷりの私見をぶちかませていただく。
ポリスのインテリ具合の凄さは、黒っぽいものの取り入れ方がまず挙げられる。元アニマルズでギンギンにブルースを弾いていたギターリストのアンディ・サマーズが放つさりげない黒っぽさ(封印したけど香ってしまう黒っぽさとも取れる)程度が、ポリスが持っていきたいベクトルだった。当時にいたるまでの成功したほとんどのバンドが、黒っぽさの取り入れ方で独自性を出した。カンタンな話、ブルースやR&Bのエッセンスはワガママな取り入れ方ができる実に便利なもので、バンドの個性をつくるのに一役買ってくれる、大変便利なファクターだった。ところがポリスの面々は黒っぽいエッセンスを知り尽くしながらも、武器としないアプローチをしたのだ。替わりになる強烈な武器が必要になり、それがあの独特で唯一無比のビート感である。レゲエ的なアプローチが多々見られ、ホワイトレゲエなるコピーが踊ったが、そんな言葉で表現しきれるほど単純なものじゃない。
ポリスの原型は、スチュワート・コープランド主導で始まったバンドだったが、想像するにデビュー前のリハーサルを繰り返しながら、スティングの天才頭脳がドンドン開花されていったのだろう。それはコープランドが持つビート感の刺激によるところが大きく、この世界一のビート野郎は脅威だったはずでありながら、スティングの想い描く世界を実現するのにはこれ以上ない存在となった。ポリスの活動休止後のスティングが、ポリス時代のような狂ったビートはまったく出していない。新しいチャレンジがしたかったとの言い訳はできるが、コープランド以外ではあんなビートは出せないだけのことだ。スティングとコープランドのコンビは、ロック界においてレノン&マッカートニーに匹敵する偉大なコンビで、ポリスの絶対的な屋台骨である。ポリスビートにとってはコープランドこそがピッチャーであり、スティングがキャッチャーである。もちろんスティングのビートだってすごいのだが、コープランドのビートを活かすことに自分のベースプレイを組み立て、天才的な音楽頭脳を駆使して、ビートを武器とする音楽づくりに徹している。数値にするのは野暮だが、7対3でコープランドがビート貢献している。たとえば『見つめていたい』のような、ただの8ビートがあれほどおもしろく聞こえることは、世界最高の武器を手に入れた世界最高の頭脳がつくりあげた、究極のカタチの1つだ。(続く)
